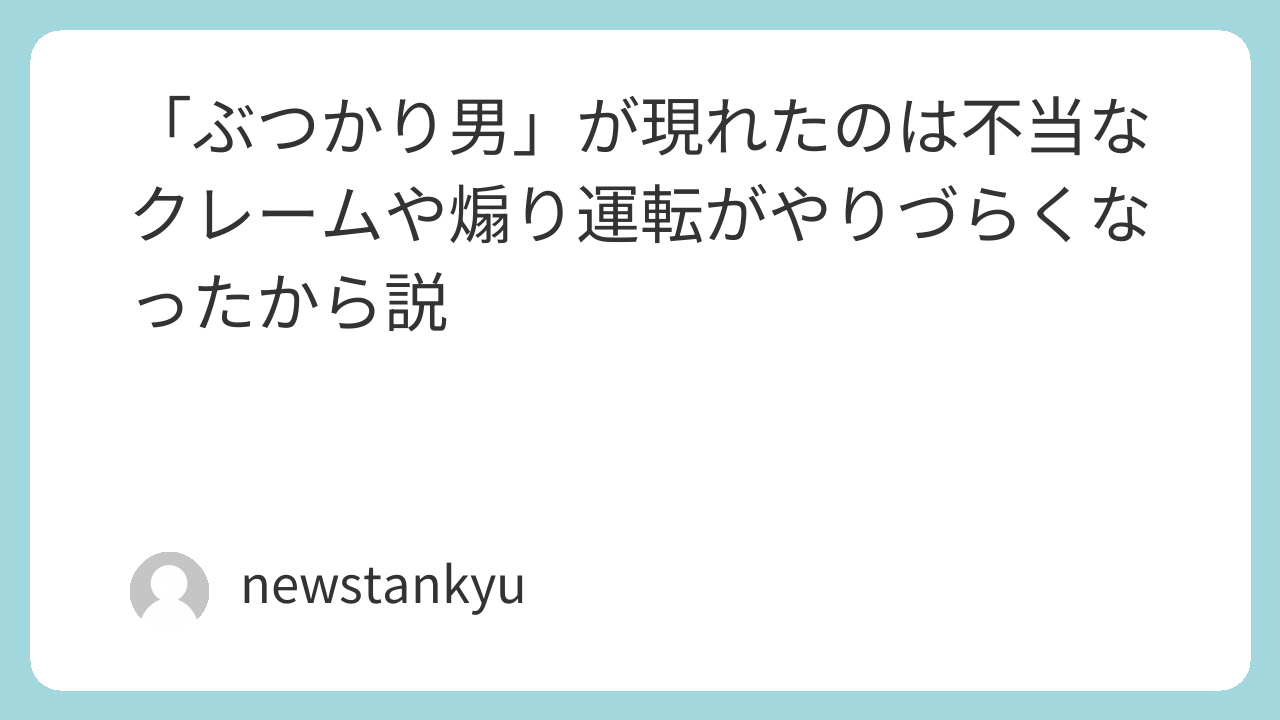一時期ほどではないが、今でもよく話題となる「ぶつかり男」「ぶつかりおじさん」という存在。ひとつ不思議だったのは、なぜ最近になって騒がれるようになったのかということだ。
おそらく最近になって「ぶつかり」を行う者が現れ、それが同時多発的に広まっていったのだろう。しかし、ぶつかり自体は今でなくともやろうと思えばやれたことだ。にもかかわらずなぜ最近になって現れたのか。
以前、ぶつかり男がなぜぶつかりを行うのかについて記事を書いた。ここではその理由を「ストレス発散のため」とし、その目的を糊塗して自らを正当化するために、相手の非をことさらに言い立てる傾向があることも述べた。
非難されるようになった「クレーマー」
ところで、昔は店員などに怒鳴り散らす者が多く見られた。しかし今はそうした不当なクレーム行為は社会的に強く非難されるようになり、店側もそうした風潮を受けて不当なクレームには強硬な対応をするようになった。
そのため、そうしたこともしづらくなり、以前に比べれば店で怒鳴り散らしたり、難癖をつけたりするような者も少なくなったのではないか。
クレーマーがなぜクレームを行うのか。理由は様々だろうが、多くは「やり返してこない弱い相手をいじめてストレス発散をしたい」からではないだろうか。本人はあくまで正当なクレームのつもりでも、無意識的にはストレス発散が目的という場合も多いだろう。
いま殺人容疑で指名手配されている八田與一もストレス発散のためによくクレームを行っていたと近しい者に語っている。1
厳罰化された煽り運転
同じように社会的非難が強まり、厳罰化された煽り運転。煽り運転を行う者の言い分をいくつか見たことがあるが、もっぱら「運転をわかってない奴に教えてやっている」「ストレス発散のため」というものだった。
こうした「相手に非がある」という主張とストレス発散をセットにしているあたりはぶつかり男やクレーマーと共通している。
煽り運転が厳罰化されたのは2018年で、これは前年に起きた東名高速夫婦死亡事故によって、煽り運転が社会的に非難されはじめたからだが、奇しくもぶつかり男が世間に知られるようになったのも同じ2018年である。2
社会的非難によってクレームや煽り運転ができなくなった者が「ぶつかり男」になった?
つまり社会的非難が強まったために、これまでのようにクレームや煽り運転でストレス発散ができなくなった。そのため新たなストレス発散の方法としてぶつかりが出てきたのではないか、ということだ。
クレーム、煽り運転、ぶつかりに共通しているのは
- 相手に精神的、物理的な暴力を振るってストレスを発散できる
- 「相手が悪い」「自分は正しいことをしている」という建前でストレス発散という本来の目的を(自分や第三者に対して)隠すことができる
- 捕まりづらい、捕まっても軽微な罰則で済む
という点だ。こういった行為を行っているのももっぱら「世の中や周囲への不満や攻撃性を溜め込んでいる中高年の男」というイメージが強い(どの程度現実を反映しているのかはわからないが)。
ぶつかりやクレームといった個別的な事象を問題視しても意味がないのでは?
これはあくまで想像で事実かはわからない。しかし、もし事実であればクレームやぶつかりなどの個別的な事象を問題視してもあまり意味はないのではないかと思う。
クレームや煽り運転ができなくなってぶつかりを行うようになったのであれば、ぶつかりができなくなれば今度はまた別のギリギリ合法的、ないし違法だが検挙されづらい方法で他人を攻撃してストレス発散をしはじめるだろう。
そうなれば対策すべきはクレームやぶつかりのような個別的な行動に対してではなく、そうした行動をとる人間に対してだ。
具体的には軽微な暴行や迷惑行為を繰り返す人間に対する刑罰を厳しくする。こうした行動をやめられない人間に精神医学的なアプローチを行う。などが考えられる。精神的な障害などのために本人の意志では抑えられないならば、そのような人間は社会安全のために隔離するべきだろう。